
- 日本語
- English
- 中文
俺はトー横キッズが好きだ。あいつらは、おもしろい。汚いけど、ギリギリを生きている。「死」選ばず、「生」をなんとか生きている。頭のいいやつもいる。俺より頭のいいやつもいる。イケてるやつだって沢山いる。日本人の持っていない、コミニュケーションに溢れている。話していて、面白い。僕は、あそこにいくと、いつもみんなに話しかけて、仲良くなったり、喧嘩したり、そう、僕自身がトー横キッズになる。
トー横には、広場のところに柵がある。
広場が解放された日、僕はその向こう側にいた。飲酒をする未成年、煙草を吸う未成年、Tiktokで踊る男女、明らかに未成年を抱きかかえる男、座り込んで酒を飲むグループ。突然始まる喧嘩、かと思えば、いつのまにか終わっている喧嘩。
これが柵の向こう側の世界だ。
大抵の人は、柵の向こう側に行かない。
柵のこちら側から、危なそうに、そして好奇の目で彼らを眺める。
まるで動物園の動物たちを眺めるかのように。
しかし、それはそれで合っている。
彼は、好きなように生きている。だから、人というよりは、どちらかと言えば、人間なのかもしれない。
意味のない、形だけの、法や規則に縛られない存在という意味で、彼ら彼女たちは動物だ。
昔は柵の外の人たちのその好奇の目に少し怒っていた自分がいた。でも今はあまりそんな気持ちはない。だって、本当に彼らは動物だからだ。
(でも、勝手に写真を撮ったり動画を撮ったりするのは、違うと思う。ちゃんと、別料金を払うべきだと思う。歌舞伎町は、無料動物園じゃないんだよ。)
つまり、僕は、トー横やトー横キッズが大好きなのだ。
でも、俺は思う。トー横キッズは、滅びるべきだ。あるいは、今のトー横のボスとされる人間がボスであるうちは、トー横という、彼ら彼女たちの場所は、とりあげられてしまうだろう。
彼は、人気者だ。一緒に歩くと、それこそ店のキャッチからホームレスのおばさんまで、色んな人に声をかけられえる。
しかし、「人気者」と「仕切り役」は違う。
彼はよく言う。
「こいつらは俺の仲間だからよお!」
「こいつらを俺は家族だと思ってる!」
じゃあ、と僕は思う。
喧嘩を、止めなよ。
じゃあ、と僕は思う。
未成年をたぶらかす男を、止めなよ。
じゃあ、と僕は思う。
ゴミを拾うように、指導しろよ。
彼は、どれもしない。
ある時、彼と喋っている時に、横で喧嘩が起きた。
(トー横というのはすぐに喧嘩が起きる街なのだ。)
その時、僕は彼に聞いた。
「止めないんですか?」
「ああ?それぞれ事情があんだから止めても意味ねえだろ」
僕はその時、少し、残念に思った。
その横では、一歩打ちどころが悪ければ、死んでしまうような喧嘩が始まりそうだったからだ。
ーーこいつらを俺は家族だと思ってる!
家族の喧嘩を止めない父親が、父親と呼べるのだろうか。
しかし、僕のその時の微かな違和感は、ふと脳を流れて消えて行った。
トー横広場は、公道である。
| 道路交通法第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 |
トー横キッズたちは、毎日のように道路交通法に違反している。
僕の好きな社会学者、宮台真司にのサインの文句にこうある。
「掟と絆」
僕はこのサインの意味をこう解している。
ーー社会には、人間が作った「法」という愚かなものが存在する。社会を生きる以上は、いかに愚かであれど、その「法」は守らなければならない。あるいは、その方が、生きやすい。しかし、「生きやすい」「生きにくい」という損得を越えたものとして、「絆」があるのだ。それは、法律や契約書の様に明文化され、また、破った場合の罰則や担保が明確に担保されているわけではない。いわば、お互いの「信用」によって成り立つものだ。私は、この二つを明確に区別したい。また、今の社会を生きるみんなにも、この二つを区別してほしい。クズはこれを混同する。あるいは、はっきりと分離する。法を守ってさえいれば、人としてこの世に生まれた以上、守ら得なければいけない「掟」を破る輩が沢山いる。そんな輩ばかりだ。儲かれば何でもあり、自分が得すれば何でもあり、そこには、「絆」がないのだ。
僕の見るところ、今のトー横キッズには、法も絆もどちらもない。
まず、「法」を守っていないことは明かだ。
では、「絆」は?
「彼女たちは助け合って生きているよ」
「彼女たちはいつも話し合って仲良しだよ」
こんな声が、トー横から聞こえる。
しかし、本当にそうなのだろうか。
ある時、座り込んで、酒を飲んでいる少年少女たちのところに、通報が入って、警察の人たちがやってきた。彼ら彼女たちは、雲の子を散らすようにどこかに行った。
僕はそれを少し離れた場所で見ていた。
逃げ遅れた二人の人間が、警察の方々に職質をされて、叱られていた。
そしてさっきまで、その輪の真ん中でみんなにちやほやされていた容姿のよい女の子は、一人、少しは離れた場所で、顔がバレないように、背を向けて、座り込んで、ストローでストロング缶を飲んでいた。
僕はそっと近づいて、話しかけた。
「さっき、みんなに揉まれていたね(笑)」
彼女は、笑った。
「逃げてきたの?」
「うん」
「大丈夫なの?もっと遠くに逃げなくて」
「いいの、もう少ししたらどこかに行くから、そしたら戻るの。」
僕は少し、がっかりした。
そこには「絆」がないのだなと、僕はなんとなく思った。
別に行って助けることはできない。
でも、彼女のサッとその場を離れて、他人のふりをして、チューチューとストロング缶を飲んで隠れる姿には、僕の思う「絆」は、なかった。
僕は、トー横に行くと、トー横キッズたちとよく喧嘩をする。
その度に、彼女たちはよくこんなことを僕に言う。
「そんな覚悟でここにきてんじゃねぇよ!」
「トー横ってのはそういう場所なんだよ!」
だいたい、言うのは未成年の子どもたちだ。
いつのまに公道が、彼らの「ここ」になったのだろう。いつのまに彼らが、公道を「そういう場所」に決めたのだろう。
彼らは家庭に居場所がなかったり、どこにも行き場のない人たち、あるいは寂しさを埋めるために集まっている人たちが多い。それは、痛いほどわかる。ここにしか居場所がない、ここで人との繋がりを実感する、それは痛いほどわかる。実のところ、僕がたまにトー横に散歩に行って、トー横キッズたちと話したり、そして時には喧嘩するのも、僕が寂しいからかもしれない。
僕は、平和主義者だ。
でも、喧嘩が大好きだ。
もちろん、自分からは売らない。
いつも、相手から売ってきてくれる。
何か薬をやっているのか、酔っているのか、彼らは喧嘩を売るのがとても上手だ。
歌舞伎町にいると色んな人に出会う、あえて名言はしない、色んな意味での怖い人と、席を共にする場面がある。
(注:ただし、反社会的勢力との交際はお断りさせて頂いています。)
僕は、そういう人たちに、殴られたことがない。(この数年の話、それより前の話は、また今度するよ。)
彼らは、ある意味で僕を認めてくれているのか、僕に手を出さない。
彼らは、見た目に傷だらけだ。傷だらけの拳、切り傷の入ったオデコ、僕は、一度、そういう人たちにボコボコにしてほしいと思って、頼んでみたことがる。
「あの、お願いします。一度、俺を本気で拉致ってボコボコにしてみてもらえませんか?大好きなあなたに、愛のある暴力を振るわれてみたいんです。」(その人の暴力には愛があると、僕は勝手に思っているのだ。)
回答?
もちろん断られた(笑)
たまに、怒る回答というか、はっきりと断ったり、強く言うべきことを言ったりしてみるのだが、せいぜいが、言葉遣いが荒くなる程度で、その人はずっと僕に対して敬語で接してくれる。
周りには、とんでもない言葉遣いで、とんでもないことをしているのに。
僕は、それを見ると、少し寂しい。
まるで自分が彼の家族じゃないみたいに感じるからだ。
話を戻そう。
トー横キッズは喧嘩を売るのがすごく上手い。そして、すぐに手が出る。
最近、トー横キッズに殴られた。この数年、怖い人に殴られるどころか、みんな敬語で接してくれるのに(よくわからないモブみたいな人ほどタメ口だ。これは僕の歌舞伎町での発見のひとつ。)あのトー横キッズにこの数年で初めて殴られたのだ。
誓って、僕から手を出していない。
また、手を出されるようなことも言っていない。
僕が何もしていないのに、あまりにも罵倒の言葉を吐き、そして僕の仲間のことまで罵倒するから、少し言い返したのだ。
すると、キックが飛んできた。
突然に腰元に当たったキックは僕の体勢を崩した、そこに強烈な左ストレート。
僕は頭の奥が真っ白になって、倒れ込んだ。
(僕は小さい頃、毎日のように親に殴られ続けていた。その時の感覚を思い出した。お父さん、殴って育ててくれて、ありがとう。)
でも、殴られたことで、倒れ込んだのは、数秒だった。
立とうと思えば、すぐに立てた。
僕は、まだまだ器が小さい、なぜ殴られたんだろう?いきなり殴るほどのことを僕はしたんだろうか?それと同意に頭によみがえる彼女の罵倒の言葉の数々、僕はじっとうずくまっていたが、それは、自分の中での怒りを、静まるためだった。頭はまだガンガンしていた。自然と湧く怒りを、僕は抑えるためにうずくまっていた。
そしてそのうち、僕は自分の怒りを完全に殺した。
そして立ち上がり、彼女に謝った。
「僕が何を君に言ったのか、僕の何が気に加わ中ったのかはわからない。でも、きっと君が手を出すことだろう、僕の何かが君の気に触って怒らせてしまったんだと思う。本当に、ごめんなさい。」
そして、僕は、彼女の目の前で、土下座をしようとした。
「やめて、いいって」
彼女はそう言って、自分の分厚いブーツ(かわいかったよ)で、コンクリートの上に、まさにそこにぶつかろうとする僕の頭の緩衝地点を作ってくれた。
「いや、土下座して詫びたいんです。」
僕は位置をズラして土下座をしようとしたが、しかし彼女はその度にそのキュートなブーツをスッと僕の頭と地面の間に刺しはさみ、僕の土下座を阻止した。
だから僕は、土下座を諦めて、その場に座り込んだ。
彼女も、しゃがみこんだ。
僕は言った。
「本当に申し訳ないと思っている。だから、こうして詫びるね」
僕は、すぐ近くにあるセブンイレブンに走って、剃刀を買った。
そして、彼女の名前を聞いて、「ごめんなさい」「ごめんなさい」と言いながら、彼女の名前を腕に刻んだ。
剃刀は三本入りだった。
彼女は僕が腕に刻むのを気にせず「一本ちょうだいよ」と言ってきた。
「いや、ダメだよ。僕が幇助しているみたいになってしまう。君は悪くないんだから、切らなくていいんだよ。」
「ちげーんだよ、気持ちいいから切りたいんだよ。」
僕は剃刀を後ろに放り投げた。
彼女はそれを拾い、友人と一緒に、僕と一緒に腕を切り始めた。
サクッ、サクッ。
「これあんま切れねえなあ」
「わー、私も切りたい」
「あー気持ちいい!やっぱリスカっていいよねえ。」
僕はまだ、その境地に達していない。
僕は、ただただ、痛い。
でも、彼女たちがすごい勢いで切るものだから、僕も追いつこうと頑張って切った。
僕たちの周りを「大変だ!」「大変だ!」と走り回って、ティッシュを渡そうとしてくれた外国の方がいたから、「大丈夫ですよ」と言って、僕はある曲を流してくれないかといった。
何だか、その曲のビートを聴いて、それに合わせて、シュッ、シュッ、とやると、上手く切れる気がしたからだ。
音楽が流れた。僕はビートに合わせて、腕を刻んだ。
たしかに、上手く刻めた。
外国の人が言った。
「血をふかないといけないよ!ケーサツくるよ!」
「誰かが通報してたらくるよ!」
たしかに。
そこからは愛の共同作業だ。
僕たちは僕たちの交じり合った血を缶ビールで流して、ティッシュで拭いて、その場を散った。
いや、散ったのは、女の子だけだった。
僕はその場で、外国の人が流してくれた音楽に浸りながら、自分の血が流れるのを眺めていた。
彼は優しい男だった。
「ダイジョウブ?ティッシュとかバンソウコウいる?」
「いや、大丈夫。ありがとう。」
彼は、ブータン人だった。
とても優しい青年だった。
恥ずかしいことに、僕はブータンがどこにあるのかわからなかった。
だから、スマホでブータンの位置を調べた。
「ここ?」
「そう!ここ。ねえ、血、ダイジョブ?」
ブータンからやってきた彼は優しい青年だった。
僕はむしろ血を流れるままにしておきたかったけれど、彼の優しさは受け取りたかったから、彼のテイッシュを受け取って、流れる血をふいた。そしておかえしに、「ありがとう」と言った。
彼は笑った。
笑顔にも色々ある。
彼の笑顔は、こんな笑顔だった。
「みんな、平和に、仲良くね」
だから僕は、さっきの喧嘩について、彼に対して、ごめんね、と思った。
それから僕は、個人的にミャンマーに関心があったので、ミャンマーの話を彼とした。
内容は省く。
いつかブータンに行くことがあれば、一緒に行こう。
そう約束して、僕たちは別れた。
たぶん、その約束は果たされない。
特にLINEも交換していないからだ。
出会って、別れ、出会って、別れ、歌舞伎町は、いや、世界は、そんな場所だ。しかし、別れても、記憶には残る。僕には彼女の、まるで世界の平和を願うような笑顔が脳裏に残る。そして同時にたまらない寂しさを覚える。
生きれば生きるほど、別れたけれど、しかし脳に残る顔が増えて、僕の脳はいつか寂しさで爆発してしまうんじゃないかと心配になる。
僕はよく誤解されるが、僕はトー横キッズたちが大好きだったし、みんなが知らないうちに色んな意味で、守ろうとしていた。その場所が、誰かに取り上げられないように、手を尽くしたりしていた。
でも、その考えが、今日、少しだけ、変わった。
今日、ある場所でぴえん女子に出会った。僕は、彼女のタクシーを停めてあげた。「たくしー!たくしー!」「そんな小さい声で叫んでも止まらないよ笑」彼女は僕が拾ったタクシーに乗って、去ろうとした。「あれ、ここに置いてあるのみもの、君が買ったやつでしょ?」「いいんだよ、置いておけば」「だめだよ、君のものなら、その辺にポイ捨てにしないで、君がちゃんと責任を持って帰って捨てないといけないよ」僕はそう言って、閉まりかけるタクシーのドアの中に彼女の買ったビンの飲み物を置いた。閉まりかけるドアの向こうから彼女はこんな感謝の言葉をくれた。「はあ?きめーんだよ、お前。」
ありがとう。
その後、僕はトー横に戻った。ある人間と話し合い、歩きあい、ご飯を食べようぜと、ある店に入った。その店に入るときに僕は言った。「人間1人と、動物1人、お願いします!」彼は、それに大笑いしていた。僕も、大笑いした。
だってっこいつは、まさに動物だからだ(笑)だから、好きんなのだ(笑)今の日本にはサイボーグみたいなやつばかりだ。動物みたいな人間が全然いない。彼は席につくと、綺麗な店員さんに絡み、持ち込んだ飲み物を平気で飲んだは飲み物はともかく、かわいい店員さんにセクハラのように大声で絡むのはよくない。しかし、少し度を超した絡み方をしているように見えた。「おい、やめろって」「ああ、いいんだって、喜んでるぜ、あいつ」実際、彼女は、戸惑いながらも、その店に初めてやってきた「動物」に面白がっているような仕草も見せていた。しかし、それ以上やると、「面白い」よりも「迷惑」が勝つと思った。だから僕は、それ以降は、彼が店員さんに絡むのを、止めた。「やめろ」「STOP、もう絡むな」「そういうこと言うのやめろって」彼は意外と素直な動物だ。そして意外と傷つきやすい動物だ。とても心の優しい動物だ。そして、だからこそ、動物のくせに人間の僕と仲が良い。
彼は店で出てきたパスタをおいしそうに食べてくれた。それを見るのが、僕は嬉しかった。彼は、ご飯を食べるときにきちんと「いただきます」と言った。そして、食べ終わってからも、きちんと「ごちそうさま」と言った。当たり前のことかもしれない。でも、悲しいことに、この当たり前のことができない人間が少なくない。
彼は動物のくせに、人間にはできないことをやったりする。僕が彼のことが好きな理由の一つがそれだ。それから、彼とはいろんな話をした。僕は、彼に提案した。「おまえ、めちゃくちゃ面白いぞ、俺がYoutubeやるからプロデュースしてやるよ。」「おう!好きに使え!俺はお前のような人間を待っていたんだよ!」
こいつは実に都合の良い動物だ。
「ったく、お前はしらじらしいな、パスタ食えるからって適当なこと言いやがって」
「ちげーよ、マジで思ってるし」
「本当か?俺はお前が好きだし、お前の吐く言葉が好きなんだ。真実をついているし、その言葉に、本当に熱がこもっているいるだろう?たまにお前、いちいち言わないけど、世界の子供たちとか、腐った世界のことを話すときに、目がうるんでるだろ。俺にはわかってるんだよ。ふだん話している時も、泣きはしていないけど、泣きゲージ10%くらいは、入っているように感じるんだよ。つまり、お前の言葉はお前の魂、熱い思いが乗っているんだよ。ぷらぷらトー横を歩いて、高架下でホームレスのように寝るのもいい、金なんていらないというのもいい。でも、金があればできることや救えることがあるあろ?だから、やろうぜ。」
「ああ?金なんていらねえ。俺は愛で生きてんだ。金なんてゴミなんだよ、資本主義はゴミだ。」
「つまり、お前にとっての通貨は愛ってこどだな。」
「そういうこと」
「ちなみに、最後に自分の金を使ったのはいつだ?」
「うーん、知らね、わすれた。後輩が飯いきましょ!とか言ってだいたい飯食わせてくれんだよ」
「お前はほんとうにおもしろいな。でもな金は持っておけよ、で、割合だけど、どうする?」
「ああ?俺を舐めんなよ。俺様とやるんだぜ。わかるか?」
「おいおい、まさか吉本ばりのお前9で俺が1かよ」
「馬鹿か!ちげえよ!全部お前にやる!俺は金はいらねえ」
「馬鹿はお前だよ、二人でやるんだろ、はんぶんこだ。」
「俺は金はいらねえんだよ!」
「まったく…でも考えてみろよ、お前はトー横のヤツらが好きなんだろ?じゃあ、たとえば月に100万かせいだらお前には50万はいるわけだ。それで、本当にお腹を空かせたガキに飯を食わせてやったり、泊まる場所がないからとホテルに連れ込まれそうになる小さい子に宿泊費を渡したり、金で救えるものはあるだろ?」
「まあ、そうだな。」
「あ、でも、思い出した。お前すぐ金なくすもんな。悪いけど、割合は、お前1、俺9にさせてもらうよ。どうせお前に渡しても”あっれ~昨日50万ここに入ってたのになくしちまった~”とか言うのが目に見えてんだよ(笑)」「ま、そうだろうな」
「誇るなよ(笑)俺がお前の分を持っておいてやるから、必要になったら言えよ、渡してやるから。」
「あーん、まあ、なんでもいい、全部やるよ、俺はお前のこと信用してっから。」
「うん。さて、お前も知ってると思うけど、俺はやると決めたらすぐにやる性格だ。一緒にやる以上、お前に逮捕されたり死なれたりしたら困る、だから、そこは気をつけてくれないか?」
「そんなもんな、なるようになるんだよ!」
「まあ、そうだけどさ、お前さっき言っただろ”トー横のみんなを守りたい”って、そして、”俺は天才だ”そうもいったよな。俺もそう思うよ。お前は生き方が美しい、そして吐く言葉も正論だ、そして言葉に熱が乗っている。自分でも言うが、俺がこんなに惚れた人間、いないぜ?お前はちゃんとやれば、マジでビッグになる。だから、ちゃんとやれよ。」
「だから言ってんだろ、俺は天才だって」
「わかってる。これを見て見ろ」
僕はそこで二次元のグラフを書いた。最初にパワーを使って事故や殺されたり長い懲役に行く人間と、そこの一番危ないところを避けて生き残って、魅力を発信し続けて、それで社会を変える人間。(難しいことを言えば、xy座標上に関数のグラフを書いて、積分をして幸福の面積を説明したのだ。)
「ほらな?今のお前みたいにいつ死んだり捕まったりしてもおかしくない。そんな生き方をするより、まあ、動物みたいに生きつつも、最低限のことは守って、長く活躍して、金を稼ぐんだよ。そして発言力も高めるんだよ。その発言力や、お前を好いて人がついてくる力を、みんなを幸せにするために使えよ。その方が、長い目で見てこのクソ社会を変えられるだろ」
彼はそれを見つめて、「たしかにな」と言った。でも僕は思った。「こいつはでも、これを絶対に守れないな」と。
でも、最初は守れなくても少しずつ信頼関係を、もっと築いて、本当にダメなことはやめるように、そういう風に接していこうと、僕は思った。
そこまで思えるほど、本当に彼はキラキラと、美しかったのだ。
「というわけで、今、ここでこの紙に約束事を書く。これだけは守ってくれ、俺のお願いだ。俺はお前がこの世界から消えてほしくない。お前は美しいんだよ。俺がここまで褒める人間はそうはいないぞ。」
「まあな」
カバンを漁ると、区議会議員さんに話に行ったときに、区役所で名誉区民賞の冊子をもらったのを見つけた。
「おい、お前は、名誉区民だ!俺が認める!書いてやるよ」
「まじかよ、ありがてえな」
僕はリュックから「新宿区名誉区民」という冊子を出した。
「なんだ、こいつら、雑魚ばっかじゃねーか!」
「おいおい、そういうことを言うなよ。この人たちも俺たちが知らないだけで偉い人かもしれないだろ。」
「ああ、まあそうかもな。」
動物は、素直だ。
「そして、僕は素直な彼の人間としての本名を聞いて、居並ぶお偉方の一番下に彼専用の欄を作った。そして本名を書いた。」
「肩書、どうする?」
「義人、だな」
「どういうことだよ」
「義に生きるってことだよ」
「センスねえな」
「そうか?」
「義は確かにある。でもお前には美しさもある。だから両方が入ったのがいいな」
彼は色々な肩書を出したが、どれもセンスがなかった。
どうやら、彼はキャッチコピーをつけるのは下手みたいだった。
「美学家、はどうだ?何が美しいか、美しさを何かというのを研究する学門があるんだ。お前はいっつも美しいとかダセえとか言うだろ?だからぴったりだろ」
「たしかに、いいな。」
「でも、美学家は研究するだけだからな、お前は行動も美しい。まあでもこれでもいいか。」
「あ、あれはどうだ?俺は真理を求めるだろ真理家はどうだ?」
「うーん…(相変わらずセンスがない)」
「哲学家はどうだ?お前の中には哲学があるだろ」
「まあ、それでいいぜ」
僕は彼の肩書の欄に「美学家」と「哲学家」と書いた。
「で、経歴のところなんだけど…」
僕はここを書くのが一番楽しみだった。
他の名誉区民の人たちは国からの勲章の受賞歴や色んな偉い業績が並んでいた。
僕は彼に聞いた。
「お前、最後に捕まったのいつだっけ?」
「ああ?しらねー、チャリのやつじゃね?」
僕はGoogleで検索した。
「あれ、暴行って書いてあるぞ、お前人殴んのかよ、どういうことだよ。」
「ああ、これな、これはニューハーフのやつと喧嘩して、交番まで押されたんだよ、散々押されて、んで、俺がちょっとポンってやったら、暴行だとさ」
(彼は僕の頭を優しくポンとした。)
「すげえな。週刊誌の捻じ曲げ能力」
「マジでびっくりしたぜ、どんだけねじまげんだよ」
「ま、それはおいといて、とりあえず、このチャリで突っ込んだやつ書いとくぞ」
「おいおい、やめろや(笑)」
「ははは」
彼の肩書には、こう書いた。
令和五年一月六日 威力業務妨害で逮捕。
「どうよ?」
「やめろや(笑)」
僕らは笑いあって、パスタを食べて、広場に戻った。
残念なことに、彼は酒を飲むと人が変わる。
僕は彼のYoutubeを本気でプロデュースしようと本気で思っていたから、日程調整をしたりするようにスマホを持てと言った。
「なくしちまうんだよ」
その通りだ。
彼は物をすぐなくす。
所有という概念が、きっとないのだろう。
(共産党の皆さま、資本主義の否定しかり、彼を次回の選挙でいかがでしょうか?)
「お前さ、でも連絡つかないのは困るよ、最初は対談形式でやりたいからさ、連絡はつくようにしてほしいよ」
「じゃあ、俺の側近のTを紹介するわ。そいつとLINEでも交換しろよ」
僕は彼と引き合わされた。
僕が彼とLINEを交換しているあいだ、酔っ払って普段と違う「彼」になってしまった彼は「良くないこと」をしていた。
僕は彼に言った。
「だからさ、そういうことをやめろってば。捕まったらできることが減るだろ。まあ、文通とかでやってやれないこともないけど、外にいた方ができることが多いだろ。」
酔った彼は別人になってしまう。
僕の言葉が耳に入らないようだ。
僕は、彼に紹介されたTという人物とLINEを交換した。
その時、Tという人物が言った。
「お兄さん、スマホいっぱい持ってるね。一台くらいこいつにあげたら?」
「いや、全部、会社の携帯なんですよ。ほら、こいつXXとかXXとかすぐ言うじゃないですか、悪いことされると会社に行きかねないので。本人が契約できるならお金渡して契約させてもいいんですけどね」
するとTは言った。
「あのさ、こいつは悪いことしねーよ。な?」
酔った彼は答えた。
「ああ、俺は悪いことなんてしねーよ!」
まさに僕の目の前で悪いことをしながら、彼はそう言った。
「最初は、とりあえず、Tさん通じて連絡を取らせてもらって、彼がちゅんとなってきたら、用意しますよ。」
僕がそう言うと、Tさんは怒った。
「あのさあ、あんた、だから言ってるだろ、こいつは悪いことしねえっての。そんで、悪いことするとか疑うなら、じゃあ一緒になんかやるとか言うなよ。お前はこいつを利用したいだけにしか見えねーぜ」
僕は、言い返したい気持ちを抑えて、黙った。
そうしていると、酔った本人が来て、僕に暴言を吐いた。
「そうだそうだ、俺はお前の魂胆なんてわかってんだよ、お前はどうせ
…」
僕は、彼に怒りたくなかったから、叫ぶようにして、踵を返した。
「わかった、わかったよ。もうこのビジネスはなし。はい、終わり。終了。さようなら。」
そして僕はそのまま家に帰った。
個人的な感情もあるのかもしれない、だが、僕は帰りに歩きながら考えた。トー横はたしかに居場所のない子どもたちや、おじさん、みんなの集まる場所だ。でも公道だ。みんなの場所だ。
なら、ゴミはちゃんと捨てるべきだ。そこで悪いこともするべきではない。
人は一人では生きていない。社会の中で生きている。
トー横の少年少女はよく、行政が私たちを排除すると不平を言う。
たしかに、よくわからず場当たり的な処置がほとんどだ。
でも、だ。
公道である以上、そこは社会だ。
公道で思い切り広がって飲んでいる、その時点で迷惑をかけているという自覚はないのだろうか。
ゴミをポイ捨てしたり、道を汚したり、している時点で、社会に迷惑をかけている自覚はないのだろうか。
トー横は、本当なら、もっと厳しく取り締まられると思う。
僕の勝手な推測だが、「かわいそうな子どもたち」という認識から、許されている部分が多分にあるように思う。
たしかに「かわいそうな子どもたち」だ。
しかし、それにしても、ゴミをポイ捨てにしない。
悪いことをしない、汚さない。
それくらいのことは、しろよ。
そんなこともせず、排除されて、それに文句を言うのは、ただの甘えでしかないぜ。
この文章を書き始めた時、タイトルに「トー横は滅びるべき」とつけた。ここまでの文章の流れが、見通せたからだ。
「居場所がない」「居場所がない」「ケーサツがウザい」「行政がウザい」そういう前に、自分が捨てたゴミくらい拾えよ。人に迷惑をかけている自覚を持てよ。そう、思ったのだ。
彼ら彼女たちは、「トー横につどうかわいそうな子どもたち」という立場に甘えているように思えた。
だが、ここまで書いて、また考えが変わった。
今、彼らや彼女たちが、そういうある種の「甘えん坊」になってしまったのは、これまでの生育環境が理由であろう。
そうであるならば、そのような甘えさえも包摂して、少しずつでも彼ら彼女たちに社会性を身に着けさせるのが、本当の大人ではなのだろうか。
トー横キッズたち、今のままだと、排除されてしまうよ。
最低限、自分のゴミを拾ったり、周りの迷惑を少しは考えるとかは、しようよ。
そうしないと、その最後の居場所も、なくなってしまうよ。
Meow
(Human, English translation)
Akane Busyoku ran for the Tokyo gubernatorial election.
And he is actively calling for votes for himself on social networking sites.
He is posting “please,” “please,” and “please,” bowing his head desperately.
This is unthinkable behavior from Akane Busy Sora, who is always bull-headed, never flattering anyone, blocks people immediately with impunity, blocks people only because they are involved with people he does not like, and asks them to do this or do that if they want him to block them, with such an attitude.
He said this, “He is always so bossy and never flirts with anyone, but this time he really wants to be the governor of Tokyo, so he is asking his followers to put aside their pride and bow down to him. He is amazing. This time he means it, let’s bet on him.” And then there are those like his cronies who take it as a sign that he is serious.
I don’t think so. It’s the opposite.
He has always made no effort to win people’s hearts and minds, and when he finally gets a chance, he jumps at it and bows his head. It’s not serious, it’s just selfish. And there is no pride in bowing down at such a single chance. It is not pride, it is just castration and arrogance.”
I think.
Recently, I have been reading a book about a politician named Shinzo Abe.
He has had an exceptional rise in the ranks of the political lower echelons.
To put it plainly for those who are not familiar with politics, he became the youngest postwar prime minister at the age of 52.
This, of course, is also amazing.
But I thought his appointment as secretary-general in his third term as prime minister was extraordinary.
I shivered when I read that scene.
But this is neither his track record nor a coincidence. Nor was it due to his family background. (Although it would not have worked in a negative way.)
When he ran for office, he never failed to make individual visits in his hometown, Yamaguchi (in one village, he went door-to-door to every house…). Even after he was elected, he went around to support the Diet members who would not be elected even if he went to their places to give speeches, even though he had no money, because he could use his body. (At the time, he was gaining popularity with the public over the North Korean issue, so it was very reassuring and gratifying for the candidate to have Shinzo Abe there to support him.)
Thus, Shinzo Abe’s exceptionally fast rise to power was the result of his tireless daily efforts.
In that sense, I think Shinzo Abe is a genius.
I like geniuses.
I like Elon Musk.
I like Haruki Murakami.
And I like Shinzo Abe.
I like Shinzo Abe, but Haruki Murakami is probably on the opposite end of the spectrum from the public’s point of view.
But I like Haruki Murakami a lot.
I have read all of his books.
I have even read books that are out of print by his own choice.
There is a certain novel that he has sealed away, which you have to go to the library in the next prefecture to read. (It is the prototype for his latest work, “The City and Its Uncertain Walls. You can read it in the chapter “In Dreams” in “The End of the World and the Hard-Boiled Wonderland” in the one on the front page. But he actually wrote this part of the work in the beginning. (I read it because I am his stalker.)
Because I am a stalker of Haruki Murakami, I have read many books written about him.
Most of them were crap.
However, this sentence from a book is as beautiful as Haruki Murakami’s writing, and I quote it here because it is first-rate writing about a genius.
| It is a very beautiful piece of writing that shows how Haruki Murakami’s seemingly aloof writing, heavily influenced by American literature, was in fact heavily influenced by “Japanese-ness” from his dudes and from careful observation of his work, and was the result of endless hard work. But again, his “creation” was not the result of an ambitious attempt to become a “personality. The “slimy as a newborn baby,” “a mass of death” (this part is emphasized with dots in the original text. It’s an old book.) In retrospect, people call those who have arrived at a “destiny” that does not belong to anyone else, while keeping “something like a baby” unseen and doing only what they are capable of doing, “genius” or “great individuality. |
I can read this sentence as applying not only to a great novelist but also to a great politician.
In this light, I can only think that Akane Busanora is licking her chops too much over the election.
If he really wants to get elected (and from his posts on social networking sites, it looks like he really wants to get elected), rather than just going out and creating a buzz, he is being too lenient, in my opinion.
Also, personally, while he is an interesting risk-taker, I would not want him as governor because of his minimal consideration for his opponents, his “exclusionary” attitude toward opposing views, and most of all, his naivete in beating up on baseless things with his own convenient storylines.
(Some of his slams are based on the wrong grounds, and some of the groups he criticizes are the opposite of what he is criticizing, and are doing good for the society.)
While talking to one local congressman, he said.
I don’t like national legislators. I hate them, I hate them, I hate them out of existence.”
I was a little disappointed to hear that.
I think it’s fine for local politics to cut budget waste and improve administration, of course.
However, there is one major premise on which all of this is based: that Japan is not involved in war.
Peace, like running water and well-maintained roads everywhere, is not something that is taken for granted.
It is based on a great sense of responsibility by someone or some people, at the cost of their own lives, and with the expectation that they will receive only criticism rather than praise from the world (but I am sure that they have faith in the future of humanity, which will be appreciated hundreds of years from now).
Peace is not something to be taken for granted.
If Japan is invaded.
Your girlfriend, A-chan, will be drugged and made crazy by people from X country, forced into a state of pleasure, but humiliated at heart, gang-raped, and finally killed by having her genitals burned with a gas burner, her eyes plucked out, and her fingers cut off one by one.
Your father, after having his wife humiliated in front of him, is stabbed with needles all over his body, dismembered, and killed while moaning in his own blood.
Your mother is gagged so that she will not die by herself, and is sexually played with from morning to night by people from other countries who also inject her with various drugs and play with her like a toy, and she gives birth to a child conceived in her. Then, in front of their eyes, the child is crushed and killed. This is repeated until their bodies are destroyed.
I believe that such things can happen in war.
I have also heard, read, and seen things similar to this, even though I am young.
This is not an imaginary story.
I think everyone is lacking a sense of crisis.
I have never experienced war, but I know how lucky I am not to have experienced war, and I know that war is very close to us, and it can happen if we make the slightest mistake.
I have no intention of becoming a politician.
I can’t be, I don’t have the qualifications to be, and I don’t have the personality to be.
But I am grateful.
I have a subordinate who used to work for the Japan Self-Defense Forces.
I know how tough it is to work for the Self-Defense Forces, as far as I have heard from him.
We are neither politicians nor SDF personnel.
So, shouldn’t we at least live our lives without forgetting to be grateful to them?
)
June 22, 2024, about 20 minutes (I forgot to measure the time)
喵喵
(人,中译本
阿金-布西谷参加了东京都知事选举
他在社交网站上积极为自己拉票
他疯狂地低头发帖,说着 “拜托 “和 “我求你了”
阿金-忙内-索拉的这种行为简直匪夷所思,他总是牛头不对马嘴,从不与人调情,肆无忌惮地立即屏蔽别人,只因为别人与他不喜欢的人有牵连就屏蔽,如果想让他屏蔽就要求对方做这做那,态度如此恶劣。
他是这样说的:”他一向牛气冲天,不会奉承任何人,但这次他真的想当东京都知事,所以要求他的追随者放下自尊,向他俯首称臣。 他真了不起。 这次他是认真的,让我们在他身上下注吧。” 还有人像他的亲信一样,认为这说明他是个好人。
我不这么认为。 恰恰相反
‘他总是不遗余力地争取民心,而当机会终于来临时,他又扑上去低头不语。 这不是认真,而是自私。 在这样一个机会面前低头,没有任何骄傲可言。 这不是骄傲,这只是阉割和傲慢。”
我想。
最近,我在读一本关于一位名叫安倍晋三的政治家的书。
他在政坛下层异军突起。
对于不熟悉政治的人来说,说白了,他是战后最年轻的首相,现年 52 岁。
这当然也很了不起。
但我认为,他在第三任总理任期内被任命为秘书长是非同寻常的。
读到这一幕,我不寒而栗。
但这既不是他的政绩,也不是巧合。 也不是因为他的家庭背景。 (尽管这不会起到负面作用)。
竞选时,他在家乡山口市的个别访问从未缺席(在一个村庄,他挨家挨户访问)。 当选后,他还跨越派别界限,甚至飞到那些即使他去支持也不会当选的议员那里,发表支持他们的演讲,即使他没有钱,因为他可以用自己的身体。 (当时他因朝鲜问题在民众中的声望越来越高,所以有安倍晋三去支持他,对候选人来说是非常放心和欣慰的)。
因此,安倍晋三异常迅速的上台是他每天不懈努力的结果。
从这个意义上说,我认为安倍晋三是个天才。
我喜欢天才。
我喜欢埃隆-马斯克。
我喜欢村上春树。
我也喜欢安倍晋三。
我喜欢安倍晋三,但在公众眼中,村上春树可能是另一个极端。
但我非常喜欢村上春树。
我读过他所有的书。
我甚至读过他自己选择的绝版书。
有一本他封存的小说,你必须去隔壁县的图书馆才能读到,我也去隔壁县的图书馆读了。 (这是他最新小说《城市和它不确定的墙》的原型)。 在头版的《世界末日与硬汉仙境》的 “在梦中 “一章中,你可以读到这篇文章。 但实际上,这篇文章是他在书的开头写的。 我读它是因为我是他的跟踪者)。
因为我是村上春树的死缠烂打者,所以我读过很多关于他的书。
大部分都是垃圾。
不过,书中的这句话和村上春树的文字一样优美,我在这里引用它,是因为它是关于天才的一流句子。
| 这是一篇优美的文字,它说明了村上春树的作品,乍一看似乎深受美国文学的影响,写得很冷漠,但实际上却深受他的公子哥儿们的 “日本性 “的影响,以及对他的作品的仔细观察,是无尽的努力的结果。 但同样,这种 “创作 “也不是 “个性 “野心熏陶的结果。 文中 “黏糊糊的,像刚出生的婴儿”,”一团死气”(这部分在原文中用点标出。 这本书有点旧)。 回过头来看,人们只把那些达到了不属于任何人的’命运’,同时又保持’类似’的东西不被发现,只做自己能做的事情的人称为’天才’和’伟大的个性’。 |
我认为这句话不仅适用于伟大的小说家,也适用于伟大的政治家。
有鉴于此,我只能认为釜山明日香在选举上舔得太多了。
如果他真的想当选(从他在社交网站上发布的帖子来看,他似乎真的想当选),而不是为了走出去而走出去,为了制造话题而制造话题,那么我认为他太天真了。
就我个人而言,我也认为他是一个有趣的冒险家,但我不想把州长一职交给他,因为他很少考虑对手,对反对意见持 “排斥 “态度,最重要的是,他天真地用适合自己的故事情节抨击毫无根据的事情。
(他的一些抨击是错误的,他批评的一些组织与他的批评截然相反,正在为社会做正确的事情)。
在与一位地方议员交谈时,他说:’我讨厌国家议员。
我讨厌国家议员。 我讨厌他们,我讨厌他们的存在。
听到这句话,我有点失望。
我认为,地方政治从预算中减少浪费和改善行政管理当然是好的。
但有一个很大很大的假设,即日本没有卷入战争。
和平就像随处可见的自来水和维护良好的道路一样,看起来是理所当然的事情,但事实上并非如此。
和平是建立在某个人或某些人的高度责任感之上的,他们以自己的生命为代价,并且知道他们不会得到公众的赞扬,而只会受到批评(但他们得到了未来人类的信任,我相信数百年后人们会对此表示赞赏)。
和平不是理所当然的。
如果日本遭到侵略。
你的女友 A 被 X 国人下药迷昏,被迫进入快感状态,但内心却受到侮辱,被轮奸,最后被用煤气炉烧毁生殖器、挖出双眼、一根根切掉手指而死。
你的父亲在妻子被玩弄于股掌之上后,被人用针刺遍全身,肢解后杀害,在自己的血泊中呻吟。
你们的母亲为了不自杀,被堵住了嘴,遭到来自其他国家的人的性玩弄,这些人还给她注射了各种药物,把她当成玩具一样从早到晚玩弄了一整天。 然后,孩子在她们眼前被碾碎并杀害。 如此反复,直到他们的身体被摧毁。
我相信战争中也会发生这样的事情。
虽然我还年轻,但我也听说过、读过、见过类似的事情。
这不是天方夜谭。
我认为人们的危机意识不够。
我没有经历过战争,但我知道没有经历过战争是多么幸运,我也知道战争离我们很近,只要我们稍有不慎,战争就会发生。
我无意从政。
我首先不能成为政治家,我没有成为政治家的素质,我也不是我应该成为的人。
但我心怀感激。
我有个下属曾经在以色列国防军工作过。
他告诉我,我知道在自卫队工作有多么艰难。
我们既不是政客,也不是自卫队人员。
因此,我们难道不应该至少在生活中不忘感激他们吗?
)
2024 年 6 月 22 日,约 20 分钟(我忘了测量时间)。
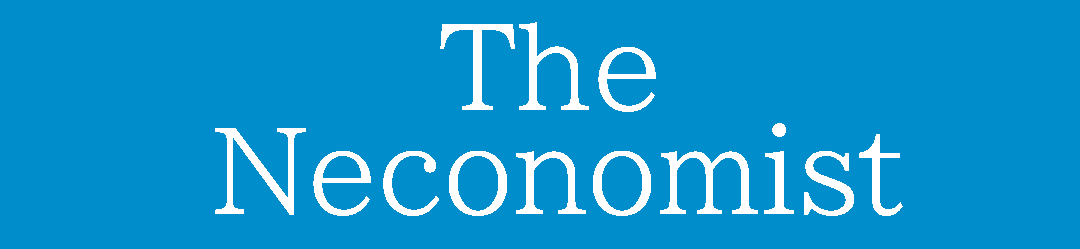

Soyez le premier à commenter